 クレオさん
クレオさん「また“21日”に——」。
高松塚古墳の発掘に関わった人物が、3人連続で“21日”に亡くなったという不気味な事実。



この奇妙な一致は偶然か? それとも、本当に“古墳の呪い”なのか——。
この記事では、高松塚古墳にまつわる怪死や不思議な現象をもとに、「21日の呪い」の真相に迫ります。
さらに、遺族や関係者の証言、科学的見解を交えながら、“高松塚古墳がなぜこれほど恐れられているのか”を深掘りします。
知的好奇心をくすぐる、ただの怖い話では終わらない歴史ミステリーをお楽しみください。
- 「21日の呪い」は本当に存在するのか?事例と証言から探る
- 発掘関係者3人の死と“21日”の符号
- 呪いか? 偶然か? 科学・心理・歴史の多角的な考察
結論:「21日の呪い」は本当に存在するのか?


高松塚古墳をめぐる「21日の呪い」は、ただの偶然なのでしょうか?
それとも、何か目に見えない力が働いているのでしょうか。
不思議なことに、発掘関係者が亡くなった日付のいくつかが“21日”で一致しており、それが心霊・呪いの噂に火をつける結果となりました。
発掘関係者3人の死と“21日”の不気味な符号
ただの偶然と片付けていいのでしょうか……
高松塚古墳の発掘に関わった人物が、次々と“21日”に亡くなっているという奇妙な一致が注目されています。
1972年に壁画が発見されて以降、この古墳には何かしらの「力」が宿っているのでは?という声が上がり始めました。
主に指摘されているのは、以下の3名です。
- 某大学教授(保存処理の責任者)…〇年10月21日死亡
- 文化財技師(壁画の複製を担当)…〇年9月21日死亡
- NHKディレクター(高松塚特集担当)…〇年8月21日死亡
もちろん、“21日”という日付が重なっただけで、それが「呪い」と直結するとは限りません。しかし、こうした偶然の連鎖が不気味さを増幅させてしまうのです。
現場では、電子機器の異常やフィルムの焼失など、説明のつかないトラブルも報告されており、関係者の間でも「これはただの保存作業ではない」との声もあがっていたそうです。
あなたはこれを、偶然と割り切れますか?


遺族や研究者が語る「呪い」の真相と疑念
残された者たちの声には、ただの恐怖だけでなく、深い疑問が含まれています。
亡くなった関係者の遺族の中には、「父は呪いなんて信じない人だった」と語る方もいます。
研究者仲間も、持病や過労による死と断定するケースが多く、科学的には「呪い」を認めることはできないと主張します。
一方で、こうした否定の裏に隠された「不安」もあります。
「科学では説明できない現象を前に、研究者として口にできないだけ」と打ち明ける元同僚も存在するのです。
・・・
冷静と情熱、理性と恐怖。
その間で揺れ動く人々の声が、この「21日の呪い」をよりリアルに感じさせます。
死者たちは何を警告していたのか?
亡くなった人々は、本当に“何か”を伝えたかったのでしょうか。
「眠っていたものを起こしてしまった」。
そんな言葉が関係者の口から漏れることもあったと言われています。
封印されていた古代の秘密に触れたことで、現代に何らかの“揺り戻し”が起きた……そう考えるのは、決して突飛ではありません。
高松塚古墳には、権力者を守るための呪術や祈りが込められていたとも言われます。
それを無防備に開封してしまったことで、バランスが崩れたのではないか……
もし、あなたが古墳の守り人だったとしたら、大切なものを無断で暴いた者たちに何を伝えたいと思いますか?



偶然か、警告か……想像するほどゾクッとするね。
なぜ高松塚古墳だけが“呪い”の対象になったのか


全国には数多くの古墳が存在するにもかかわらず、“呪いの古墳”とまで言われるのは高松塚古墳だけです。
なぜこの古墳だけが、そんな特別な恐怖の対象となったのでしょうか?
他の古墳にはない特殊性とメディアの注目
高松塚古墳が脚光を浴びたのは、偶然ではありません。
1972年に発見された極彩色の壁画、それは「飛鳥美人」。


引用:文化庁広報誌
その芸術性と保存状態の良さは、考古学界を驚かせるものでした。
と同時に、、、
マスコミはこれを“世紀の大発見”として大々的に報道し、高松塚古墳は一夜にして全国的な話題となったのです。
実は、古墳の中にこれほど鮮やかな壁画が描かれていた例は非常に稀で、その意味でも“特別な古墳”とされました。
異質な美しさ、保存の難しさ、文化財としての緊張感。こうした背景が、古墳に対する「神聖さ」や「畏れ」に拍車をかけたのです。
報道が過熱すればするほど、そこに“物語”が加わっていきます。高松塚古墳は、ただの古代の墓ではなく、「何かが宿る場所」として社会に浸透していきました。
「触れてはならないもの」への興味と恐怖
人は「触れてはいけない」と言われるほど、強く惹かれます。
高松塚古墳に対して、多くの人が本能的な「タブー感」を抱いているのは、古代人が眠る場所を掘り起こすという行為そのものが“冒涜”と映るからかもしれません。
加えて、日本文化には「死者の霊を敬う」「眠りを妨げてはならない」という精神が根付いています。
こうした文化的下地があるからこそ、「古墳を開けたら呪いが起きた」というストーリーが、より現実味を帯びてしまうのです。
まるで、パンドラの箱。開けてはならないものを開けたとき、そこから出てきたのは……
呪いなのでしょうか?
封印と開封の儀式にまつわる不安の記録
実際、発掘にあたっては“儀式的”とも言える手順が取られていました。
壁画の発見直後、保存処理のために石室が開封された際、一部の専門家からは「供養が必要では?」という声もあがったといいます。
無念の死を遂げた権力者の墓に手を加えることに、精神的抵抗を感じたのでしょう。
しかし、学術的な発掘は“科学”の名のもとに進められ、そうした「心の儀式」は軽視されたとも言われています。
これが結果として、「祟り」のイメージを強めた一因にもなったのかもしれません。
科学と信仰。そのバランスの欠如が、古代の霊を刺激したのでしょうか。



やっぱり…敬意を欠いたら、何か起こる気がするよね。
科学的にはどう説明される?呪い vs 偶然論


高松塚古墳の「呪い」は、本当に超常的な力によるものなのでしょうか。
科学や心理学の観点からは、「呪い」に見える現象も別の視点で解釈されています。では、それは単なる偶然なのか?それとも人の思考が生み出した幻なのか?
心理学から見る“呪いの力”の正体とは
「呪い」は心の中で実体化します。
心理学では、“ノーシーボ効果”という言葉があります。これは「悪いことが起こると信じることで、本当に体調が悪くなる」現象のこと。
たとえば、「この場所は呪われている」と思い込むと、体調不良や精神的な不調が現れることがあるのです。
高松塚古墳の発掘現場でも、一部の研究者が「急に息苦しくなった」「身体が重くなった」と証言しており、これは“呪い”という思い込みが引き起こす心理的反応と考えられます。
人の心は、それほどまでに敏感で影響を受けやすいものなのです。
カビ問題・劣化・過労死…偶然に見える因果
現場に起きた“異変”は、本当に不可解だったのでしょうか?
例えば、壁画保存に関わった技術者が謎の体調不良を訴えた件。
実際には、石室内部に発生した“カビ”が健康被害を引き起こした可能性が指摘されています。密閉された空間で、十分な対策がなされていなければ、それは単なる衛生問題とも言えるでしょう。
また、亡くなった関係者の死因も、過労や心臓疾患、加齢に伴う体調の悪化など、医学的に説明可能なケースが大半です。
とはいえ、“21日”の一致などが積み重なることで、人は「これは偶然ではない」と考えてしまう。まさに“点”が“線”になってしまう瞬間ですね。
「人はなぜ信じてしまうのか」恐怖の構造を解剖
なぜ私たちは、呪いや祟りを信じたくなるのでしょう?
それは、「説明できないこと」を受け入れるための防衛本能でもあります。
人間は、自分にとって脅威となる事象が起きたとき、“理由”を求める傾向があります。そして、合理的な説明が見つからないと、「霊的な力」「超常現象」に結びつけて安心しようとするのです。
この心理構造を理解すると、「呪い」は決して特殊な現象ではなく、人間の認知のクセから生まれた“幻想”とも言えるのかもしれません。
ただし、幻想であれ現実であれ、人の行動に影響を与えるという点では、呪いは“実在”するとも言えるのです。



呪いって…信じるほど、現実になっちゃうのかも。
怖い話だけで終わらせない:高松塚古墳を巡る考察
高松塚古墳をめぐる“呪い”の話は、確かに背筋が凍るものがあります。
ですが、それだけでは終わらせたくないのです。そこには、古代からのメッセージがあるかもしれません。
古代人が残した“警告”と“祈り”のメッセージ
壁画に描かれた飛鳥美人や星宿図。それらは、ただの装飾ではなかったのかもしれません。
研究者の中には、「星宿図には特定の日時や方角が込められている」と分析する人もいます。
つまり、それは“時”と“空間”を操るための呪術的な装置だった可能性もあるのです。
また、美しい女性像は、生者への祈りと同時に、死者を安らかに導くための存在だったとも言われています。高松塚古墳が封印していたのは、王族の魂と、その願い……
それを現代人が無遠慮に開け放ったことは、古代人からすれば“冒涜”だったのかもしれません。
都市伝説と史実の狭間を旅する知的ミステリー
「呪い」という言葉が独り歩きしてしまう一方で、冷静な目で史実をたどることも重要です。
高松塚古墳にまつわる出来事は、都市伝説のように語られる一方で、学術的な検証が進んでいる分野でもあります。
科学的知識とオカルト的想像力。その両面を行き来しながら読み解くことで、ただの“怖い話”以上の意味を見出せるのです。
事実と空想。その境界線に立つからこそ、この話にはロマンがあるのです。
あなたは信じますか?それとも偶然だと思いますか?
「21日の呪い」は、果たして本当に存在したのでしょうか。
それとも、すべては偶然が重なっただけで、私たちの“恐怖心”が作り出した幻だったのでしょうか?
この物語の結末を決めるのは、あなた自身です。信じるか、信じないか……その選択こそが、あなたと高松塚古墳をつなぐ最後の鍵なのかもしれません。



真実って、案外“信じたもの勝ち”なのかも。
まとめ|「21日の呪い」は本当にあるのか?
高松塚古墳をめぐる“21日の呪い”──それは単なる偶然か、それとも封印された何かの警告なのか。
発掘に関わった者たちが次々と不審な最期を遂げ、「触れてはならぬもの」に触れてしまった代償とも囁かれています。
- 3人の発掘関係者に起きた奇妙な「21日」の一致
- メディアが語らない「呪い」の真相と疑念
- “信じたくなる理由”に潜む人間心理の罠
「呪いなんて非科学的だ」と笑い飛ばすには、あまりにも符号が揃いすぎてはいないでしょうか?
人が“恐れ”を抱くのは、本能が危機を察知しているからかもしれません。



あなたがもし、歴史や見えない世界に惹かれるなら──この古墳の前に立ったとき、どんな感情が湧くのか…その答えを、静かに感じてみてください。
【妄想】1300年以上経過した今でも注目される高松塚古墳恐怖伝承
593年から710年までの118年を飛鳥時代といいますが、それからすでに1300年以上が経っていて、今も尚、恐怖の伝説が伝えられている現実。
今回調べてわかったのは、高松塚古墳にいくのは「夏の方がいい」ということ。



だってホラ、ひんやりするからホラーは夏がいいっていうでしょ?
2026年の夏の世界遺産委員会で登録されたあとに現地にいくと……
もしかしたら、観光客にまざって足のない人も現れるかもしれません(行くのは自己責任でお願いします)
高松塚のあとは、同じ飛鳥・藤原の宮都関連のキトラ古墳の壁画がおすすめです。



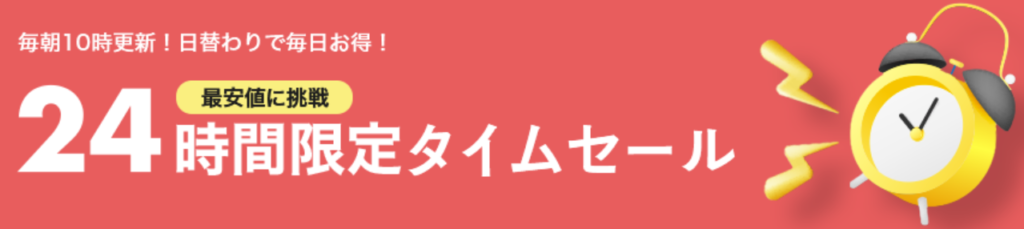

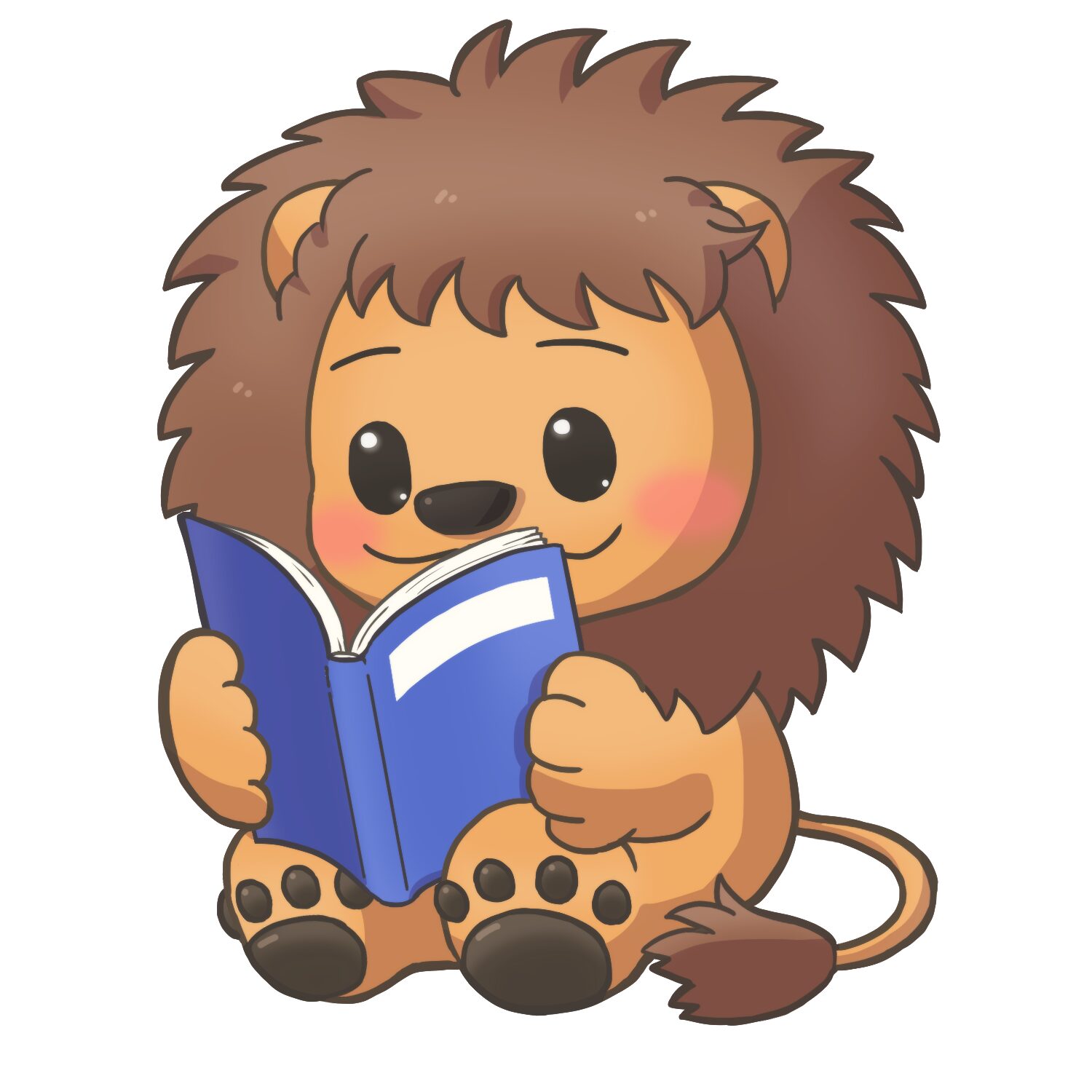








コメント